本を持ち運ぶとき、意外と気になるのが「重さ」ではないでしょうか。
雑誌や単行本、文庫本などはそれぞれサイズやページ数、紙質によって重さが大きく変わります。
本の重さを知っておくと、通勤・通学のカバンが軽くなったり、旅行の荷物をうまく調整できたりと、日常生活に役立つことがあります。
この記事では、雑誌・単行本・文庫本・ハードカバーの重さの目安をわかりやすく比較しながら紹介します。
さらに、自宅で簡単にできる本の重さの測り方や、用途別におすすめの本選びも解説。
「どんなシーンで、どの本を選ぶべきか」が分かれば、もっと快適に読書を楽しめるはずです。
本の重さの目安とは?

ここでは「本の重さ」をテーマに、その基本的な目安を解説していきます。
普段何気なく持ち歩いている本も、実はサイズやページ数によって大きく重さが変わるんです。
知っておくことで、荷物の調整や持ち運びの工夫に役立ちます。
なぜ本の重さを知ることが大切なのか
本の重さを把握しておくことで、カバンの軽量化や荷物バランスの工夫につながります。
特に毎日カバンに本を入れている人は、数百グラムの違いで負担感が変わることもあります。
※本記事の内容は一般的な生活上の工夫についての情報であり、医学的な効果を保証するものではありません。
自分の生活スタイルに合った重さの本を選ぶことが、快適な読書時間につながります。
| 状況 | 重さを知るメリット |
|---|---|
| 通勤・通学 | 荷物を軽くすることで体の負担感が和らぐ場合がある |
| 旅行 | 荷物の重量制限に対応しやすい |
| 日常の持ち歩き | バッグが軽くなり快適 |
本の重さに影響する要素(サイズ・ページ数・紙質)
本の重さは「サイズ」「ページ数」「紙質」に大きく左右されます。
サイズが大きいほど紙面が広がり、その分紙の使用量が増えます。
ページ数が多ければ当然重量も増えます。
さらに、厚手の紙や光沢紙を使った雑誌などは、同じページ数でも重さが変わります。
つまり、本の重さは一概に決められず、複数の要素が組み合わさった結果なのです。
| 要素 | 影響 |
|---|---|
| サイズ | 大きいほど重くなる傾向 |
| ページ数 | 増えるほど重量が増す |
| 紙質 | 厚手や光沢紙は重くなる |
雑誌の重さをタイプ別に比較
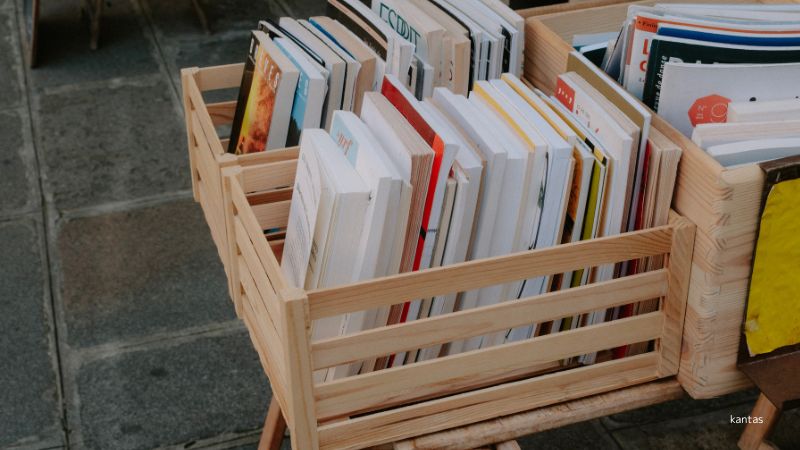
次に、雑誌のジャンルごとにどのくらい重さが変わるのかを見ていきましょう。
ファッション誌やスポーツ誌、実用誌では、サイズや厚みの違いから重さに大きな差があります。
ここでは代表的な雑誌を例に解説します。
ファッション誌の平均的な重さ
ファッション誌はA4サイズで厚さ1センチ前後が多く、重さはおよそ650グラム程度です。
紙質がしっかりしているため、持ったときのずっしり感があります。
見た目の高級感がある一方で、持ち歩くには少し負担になる重さです。
| 種類 | サイズ | 重さの目安 |
|---|---|---|
| ファッション誌 | A4、厚さ約1cm | 約650g |
スポーツ誌や実用誌の軽さと特徴
スポーツ誌は比較的薄く、平均で約250グラムと軽量です。
一方で実用誌は200〜300グラム程度が多く、趣味や教育に特化した内容が中心です。
雑誌でもジャンルによって軽量かつ持ち運びやすいタイプがあるので、用途に応じて選びやすいのがポイントです。
| 種類 | 重さの目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| スポーツ誌 | 約250g | 薄くて軽く持ち運びに便利 |
| 実用誌 | 200〜300g | 趣味や教育関連、軽めの構成 |
単行本と文庫本の重さの違い

ここでは、マンガ単行本や文庫本など、持ち運びの定番といえる本の重さについて解説します。
サイズの違いによって重さが変わるので、カバンに入れるときの負担感も異なります。
普段の読書スタイルに合わせて選ぶ参考にしてください。
マンガ単行本(B6・A5サイズ)の重さ
マンガ単行本は多くがB6サイズで、150〜200グラム程度が一般的です。
これはペットボトルのキャップを集めたくらいの軽さで、片手で楽に持てます。
A5サイズになると少し大きくなり、200〜250グラム程度に増えます。
サイズが大きい分読みやすいですが、持ち歩きの頻度が高い人は少し重さを意識した方がよいでしょう。
| 種類 | サイズ | 重さの目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| マンガ単行本 | B6 | 150〜200g | コンパクトで軽量、日常的に持ち運びやすい |
| マンガ単行本 | A5 | 200〜250g | やや大きめで読みやすいが重さも増す |
文庫本の軽さと持ち運びやすさ
文庫本は平均200グラム前後と、とても軽量です。
片手で持ちやすく、ポケットサイズのものもあるため、通勤電車や旅行先に最適です。
荷物を少しでも軽くしたいなら、文庫本が一番の味方です。
| 種類 | 重さの目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 文庫本 | 約200g | 小型で軽く、持ち運びに便利 |
ハードカバー本の重さと特徴

続いて、重厚感のあるハードカバー本について見ていきましょう。
ソフトカバーよりも耐久性や見た目の高級感がありますが、その分重さは増します。
特に長時間持ち歩くときには注意が必要です。
一般的なハードカバーの重さ
一般的なサイズのハードカバー本は、およそ450グラム程度とされています。
これは缶コーヒー1本分くらいの重さで、長時間持っていると少しずっしり感じます。
「しっかりした本を読んでいる」という満足感は大きいですが、カバンに複数冊入れるのは負担になりやすいです。
| 種類 | 重さの目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| ハードカバー | 約450g | 耐久性があり高級感もあるが重め |
専門書や大判サイズのケース
専門書や大判サイズのハードカバーはさらに重量が増し、1キログラムを超える場合もあります。
特に写真集や美術書は厚紙や特殊な印刷が使われるため、持ち歩くよりも自宅でじっくり読むのに向いています。
用途によっては「重さそのものが品質の証」ともいえるでしょう。
| 種類 | 重さの目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 専門書(大判) | 700g〜1kg以上 | 分厚く内容が濃い。携帯には不向き |
| 写真集・美術書 | 1kg以上 | 高品質な印刷で重いが見応えあり |
本の重さを実際に測る方法

ここでは「本の重さを正確に知りたい」と思ったときに役立つ方法を紹介します。
ちょっとした工夫で、手元にある本の重さをすぐに確認できます。
購入前に重さを把握しておきたい人や、旅行の荷物を調整したい人におすすめです。
キッチンスケールでの計測
最も手軽な方法は、自宅にあるキッチンスケールを使うことです。
料理用のデジタルスケールなら、1グラム単位で正確に測定できます。
普段の料理道具が、本の重さを測るツールとしても活躍するのは意外ですよね。
| 方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| キッチンスケール | 手軽で正確に測れる | 本が大きいと載せにくい |
カタログや出版社データを参考にする
インターネット通販サイトや出版社の公式ページでは、本のサイズや重量が記載されている場合があります。
購入前にその情報を確認すれば、持ち運びのしやすさを事前に判断できます。
ただし、記載がない場合もあるので、確実に知りたい場合はやはり実測が安心です。
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 出版社データ | 購入前に確認できる | すべての本に記載があるとは限らない |
用途別おすすめの本の選び方
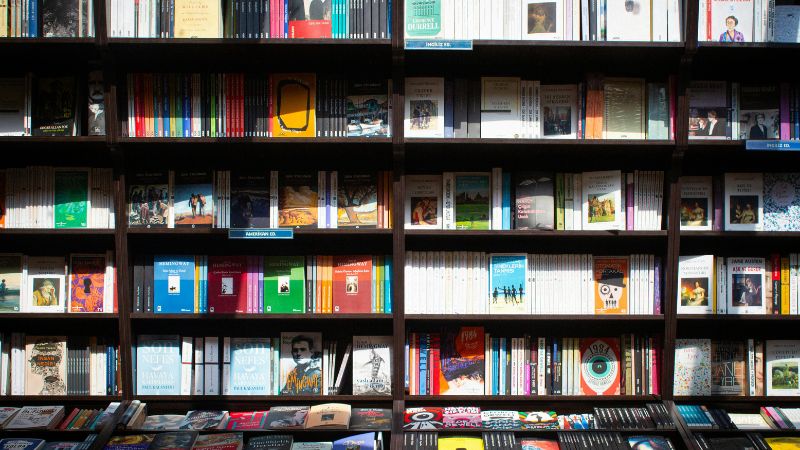
最後に、シーンごとに適した本の重さについて考えてみましょう。
通勤や旅行、リラックスタイムなど、読書の場面によって選ぶべき本は異なります。
重さを意識して選ぶだけで、読書の快適さがぐっと上がります。
通勤・通学で持ち歩きやすい本
毎日の移動時間に本を読みたい場合は、軽量な文庫本や薄めの単行本がおすすめです。
バッグに入れても重さを感じにくく、片手で読みやすいのが魅力です。
マンガ単行本のB6サイズや文庫本なら、負担なく読み続けられます。
| 用途 | おすすめの本 | 理由 |
|---|---|---|
| 通勤・通学 | 文庫本、B6単行本 | 軽くて片手で読める |
旅行に持っていくならどんな本が最適?
旅行では荷物をできるだけ軽くしたいものです。
そのため、コンパクトな文庫本や電子書籍リーダーがベストです。
旅行先での快適さを考えると、「軽さ」を最優先にした本選びが正解です。
| 用途 | おすすめの本 | 理由 |
|---|---|---|
| 旅行 | 文庫本、電子書籍 | 軽くて場所を取らない |
まとめ|本の重さを知って快適な読書スタイルを
ここまで、本の種類ごとの重さや測り方、用途別の選び方を紹介してきました。
最後に、重さを意識することで得られるメリットと、シーンごとの選び方のコツを整理します。
自分に合った一冊を選ぶ参考にしてみてください。
重さを意識することで得られるメリット
本の重さを知っておくと、荷物全体のバランスを考えやすくなります。
特に通勤・通学では、毎日の移動が少しでもラクになります。
本の重さを意識することは、快適な読書環境をつくる第一歩です。
| メリット | 具体例 |
|---|---|
| 体への負担軽減 | 重い荷物を避けることで体への負担を軽減しやすくなる |
| 荷物管理が楽に | 旅行や出張のパッキングで便利 |
| 読書習慣が続く | 気軽に持ち運べることで読書時間が増える |
シーンに合わせた本選びのコツ
日常生活のシーンごとに、適した本のタイプは変わります。
軽量な文庫本や薄い雑誌は移動中にぴったりですが、自宅でじっくり楽しみたいならハードカバーや写真集も選択肢に入ります。
重要なのは「どこで、どのように読むか」を意識して選ぶことです。
| シーン | おすすめの本 | 理由 |
|---|---|---|
| 通勤・通学 | 文庫本、軽量単行本 | 片手で読みやすく持ち運びが楽 |
| 旅行 | 文庫本、電子書籍 | 軽くて荷物がかさばらない |
| 自宅 | ハードカバー、美術書 | 落ち着いて腰を据えて楽しめる |


