昔から何気なく使っている「ハンガー」という言葉。でも、ちょっと待ってください。おじいちゃんやおばあちゃんが「衣紋掛け」なんて言葉を使っていた記憶はありませんか?実はハンガーにも、時代を感じる素敵な“昔の呼び方”があるんです。
この記事では、そんな懐かしい言葉の背景や、呼び方が変化した理由をわかりやすくご紹介します。身近な生活用品ひとつとっても、そこには日本の文化や暮らしの変遷がぎゅっと詰まっているんですよ。
ハンガーの昔の呼び方って何?知ってスッキリ!検索意図を解決

ハンガーの昔の呼び方について、もっともよく使われていた表現や、家庭ごとのバリエーションを紹介します。
一番有名なのは「衣紋掛け(えもんかけ)」
ハンガーの昔の呼び方で最も広く知られているのが、「衣紋掛け(えもんかけ)」という言葉です。なぜこの名前が使われていたのかというと、着物を掛けておく道具として使われていた背景があるんですね。
着物はたたんでしまうとシワになりやすいため、風通しのいい場所に掛けておく文化が根付いていました。「衣紋」とは、和服の襟元あたりのこと。この部分を美しく保つために専用の道具として存在していたのが「衣紋掛け」です。
つまり、今の“ハンガー”というより、もっと丁寧に衣類を扱うための道具として生活に溶け込んでいたのです。
「かけ」や「洋服かけ」などの言い回しも
昔の家庭では、「ハンガー」と言わずに「かけ」とだけ呼ぶケースもよく見られました。これは略称のようなもので、「洋服をかけるもの」=「かけ」という感覚ですね。また、「洋服かけ」や「服かけ」など、使う家庭によって多少呼び方に差があったようです。
特に地方では、英語があまり浸透していなかった時代に、機能的な名前で呼ぶ傾向が強かったと考えられます。そういった呼び方が残っている家庭では、今でも「ハンガー取って」ではなく「かけ取って」と言う人も。
このように、昔の呼び方には機能をそのまま表現したシンプルな魅力がありました。
家庭や地域で呼び方に違いがある理由
ハンガーの昔の呼び方は、家庭や地域によって本当にさまざまでした。その理由は、標準語が今ほど強くなかったことと、生活文化の差が大きかったことにあります。テレビや雑誌で“ハンガー”という言葉が一般化する前までは、地域ごとの言い方が自然と受け継がれていたのです。
たとえば関西圏では「えもんかけ」と言うことが多く、関東圏では「かけ」のほうがよく使われていた、というような違いも。家族の中でも、祖父母と孫世代で言葉がまったく違う…なんて場面もよくありました。
英語の“ハンガー”が定着した時期とは?
“ハンガー”という言葉が一般家庭に浸透したのは、昭和中期以降だと考えられています。
戦後の復興期にアメリカ文化が日本に一気に広まったことで、衣類の保管方法にも変化が生まれました。洋服を日常的に着るようになったことから、英語の“hanger”がそのまま使われるようになったんですね。
百貨店やカタログ通販、テレビCMなどでも「ハンガー」という単語が当たり前に使われ始め、徐々に定着していきました。今ではすっかり日本語のように使われていますが、その背景には時代と文化の大きな転換があるんです。
知って納得!なぜ昔は「衣紋掛け」と呼ばれていたの?

「衣紋掛け」という言葉の成り立ちや、和服文化との関係について掘り下げていきます。
和服文化との深い関係があった
昔の日本では、洋服よりも和服が日常の装いでした。そのため、衣類の収納や保管の方法も和服に適したスタイルが基本になっていました。「衣紋掛け」は、そうした生活に欠かせない道具だったわけです。
和服は折りジワがつきやすく、特に襟まわりをきれいに保つことが求められていました。だからこそ、襟元=「衣紋」を守る専用の器具として、衣紋掛けが長年使われ続けたんですね。
このように、衣紋掛けという言葉には、和の暮らしの知恵がぎっしり詰まっているのです。
日本家屋での生活様式が背景に
和室中心の暮らしだった時代には、洋服ダンスやクローゼットはほとんど存在しませんでした。そのかわりに、風通しの良い場所に衣紋掛けを設置し、着物をさっと掛けておくという使い方が一般的でした。湿気の多い日本の気候では、こうした“吊るして保管する”方法が理にかなっていたのです。
また、木製のしっかりした作りの衣紋掛けは、家具としても美しい存在感を放っていました。現代のハンガーと違い、生活道具としての重みがありました。
明治・大正・昭和で変わった生活習慣
明治以降になると、徐々に洋装が広まり始めました。とくに都市部では、スーツやワンピースなどが一般化し、それに伴ってハンガーのような道具も普及していきます。そして戦後の高度経済成長期には、一気に洋服中心の生活へと変わりました。
その結果、「衣紋掛け」ではなく「ハンガー」が主流になっていったのです。でもこの変化の過程には、明治・大正・昭和それぞれの時代背景が色濃く反映されていて興味深いですよね。
「衣紋掛け」の語感が伝えるやさしさ
「衣紋掛け」という言葉、音の響きにどこかやわらかさを感じませんか?
“えもん”という言葉には、衣服の襟元を思い浮かべるような繊細さがあり、“掛け”という単語には、手間をかけて丁寧に扱うという日本人らしい感性がにじみ出ています。
機能的にはハンガーと同じ道具ですが、「衣紋掛け」と呼ぶことで、物を大切にする気持ちが込められているようにも思えます。言葉そのものに時代の空気や価値観が表れているのが面白いところです。
知識としても面白い!言葉の移り変わりを楽しもう

ハンガーという言葉の広まりと、それにともなう言葉の変化について、背景やきっかけを詳しく見ていきましょう。
「ハンガー」はカタカナ語としてどう広まった?
「ハンガー」はもともと英語の“hanger”が語源です。
この言葉が日本で一般的になったのは、昭和の中頃。戦後の高度経済成長の時代に、欧米のライフスタイルがぐっと身近になったことで広まっていきました。洋服文化が浸透するにつれ、それを保管する道具としての“ハンガー”も一緒に定着していったのです。
百貨店の商品名やテレビCM、さらにはカタログなどでも「ハンガー」という言葉が当たり前のように使われ始め、徐々にその呼び方が全国に広がっていきました。
つまり、外国の言葉がそのまま“カタカナ語”として日常会話に馴染んでいった流れの中に、ハンガーもあったわけですね。
学校教育やメディアの影響も見逃せない
言葉の広まりには、メディアと教育の影響も見逃せません。小学校の家庭科や道徳の授業でも、昭和後半には「ハンガー」という言葉が普通に使われるようになっていきました。テレビ番組や子ども向けの本、教育番組などでも「ハンガー」が標準語として取り上げられる機会が増えたんです。
また、漫画やアニメの中でも登場人物が「ハンガー取って」と言う場面があり、それが当たり前の感覚として定着していった側面もあります。こうした“生活に溶け込む言葉”は、教育やメディアから自然に広まっていくことが多いんですね。
呼び方の変化が教えてくれる時代の流れ
呼び方の変化というのは、単なる言葉の違いではなく、時代の変化そのものを映し出しています。
たとえば「衣紋掛け」は和服中心の暮らし、「ハンガー」は洋服中心のライフスタイルを表しているとも言えますよね。同じ道具であっても、使われる環境や社会の価値観が変わることで、名前すら変わっていくんです。
言葉の変化をたどっていくと、その背景にある暮らしや文化の移り変わりが見えてきて面白いですよ。だからこそ、昔の言葉と今の言葉を比較してみることには大きな意味があります。
昭和レトロが再注目されている理由
最近では、昭和レトロな言葉やアイテムが再び注目されています。その背景には、どこか懐かしく、あたたかい雰囲気を求める人が増えているという流れがあるように感じます。
レトロなデザインや古き良き表現に惹かれる若い世代が増え、SNSなどでも「#昭和レトロ」のハッシュタグが盛り上がっていますよね。「衣紋掛け」といった昔の言葉も、そうしたレトロブームの中で再び見直されているのです。
モノだけでなく、言葉にも“癒やし”や“ノスタルジー”を感じる人が増えてきたのかもしれません。
今こそ見直したい!昔の言葉に宿る温かさ
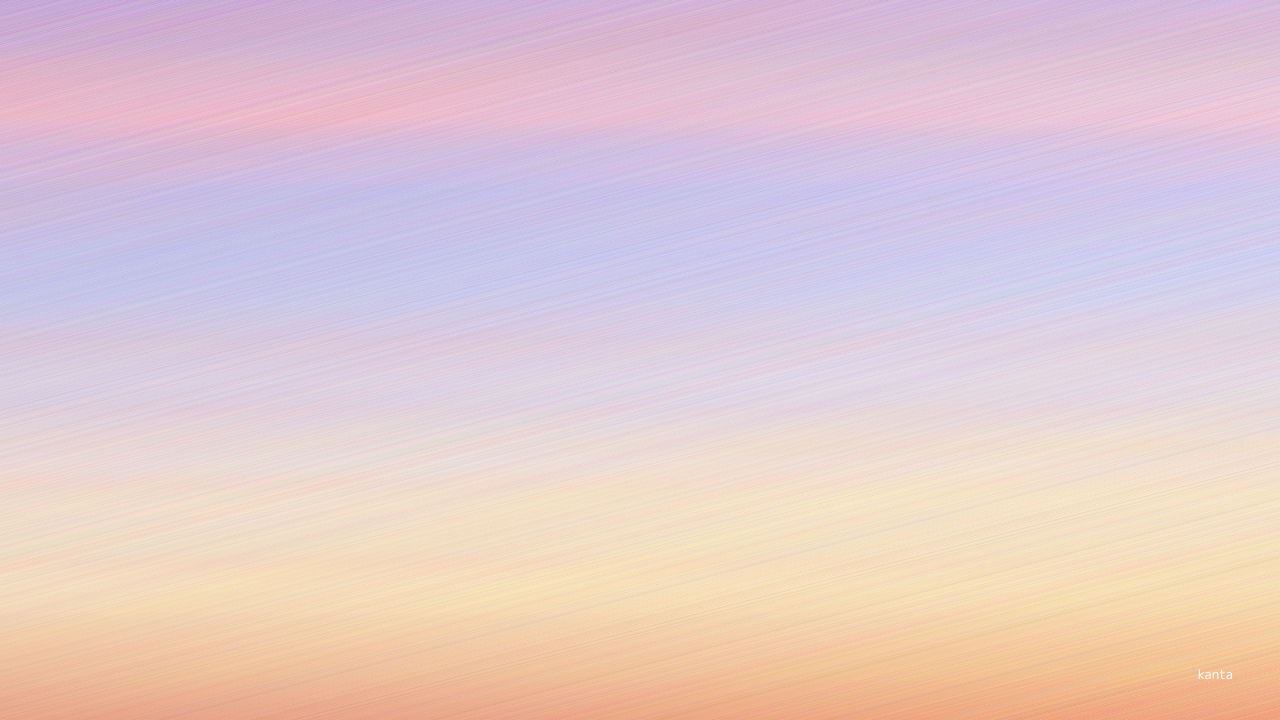
昔ながらの言葉に込められたやさしさや意味を、現代の視点から改めて味わってみましょう。
「衣紋掛け」と呼ぶことで感じる懐かしさ
「衣紋掛け」という言葉を聞くと、どこかホッとするような感覚になりませんか?それは、丁寧に暮らしていた昔の人たちの息遣いが、その言葉に残っているからだと思うんです。たとえ今の暮らしが便利になっても、物を大切に扱う心は忘れたくないですよね。
呼び方を少し変えるだけで、毎日の何気ない動作にも気持ちがこもる気がします。そんな“言葉の力”を改めて感じさせてくれるのが、「衣紋掛け」なんですよ。
親世代との会話のきっかけにもなる
昔の呼び方を知っていると、ちょっとした会話のきっかけにもなります。
たとえば実家に帰ったとき、「あれって昔、衣紋掛けって言ってたよね」なんて話題を振ると、思い出話がポロポロ出てくることも。こういう何気ないやりとりって、意外と心に残るものなんです。
言葉は世代をつなぐ架け橋にもなりますし、共通の話題として家族のつながりを深めるきっかけにもなるはずです。昔の言葉を知っていると、ちょっと得した気分になりますよ。
生活の中にある“言葉の物語”を大切に
暮らしの中には、昔ながらの言葉がたくさん残っています。それぞれの言葉には意味があって、背景には必ずストーリーがあります。「衣紋掛け」もそう。和服のある生活があって、丁寧な暮らしがあって、そこにこの言葉が根づいたんですよね。
現代ではすっかり忘れられがちですが、こうした“言葉の物語”を掘り起こしていくことって、意外と豊かな時間なんです。物の名前だけでなく、その奥にある想いや文化を感じ取っていきたいものですね。
昭和の言葉で暮らしに彩りをプラス
言葉をちょっと変えてみるだけで、いつもの暮らしに彩りが加わることもあります。たとえば「ハンガー」ではなく「衣紋掛け」と呼んでみる。それだけで、なんとなく空気感がやわらかくなる気がしませんか?
古い言葉を取り入れることで、会話や雰囲気に温かみが出るんです。昭和の言葉には、そんな魅力がたくさん詰まっています。今の暮らしの中にも、ちょっとだけ昔の言葉を取り入れてみると、気持ちに余白が生まれてくるかもしれません。
まとめ
「ハンガー」の昔の呼び方から見えてくるのは、暮らしの移り変わりと、言葉に宿る文化や感性です。
「衣紋掛け」という言葉には、和の心と丁寧な暮らしが感じられます。
言葉の違いを楽しみながら、日常の中にある小さな発見を大切にしていきたいですね。


